
近年、ビジネスやマーケティングの現場では「NI分析」という言葉を耳にする機会が増えています。
ですが、まだあまり一般的に浸透していないため、「NI分析って何?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、NI分析の概要やメリット、実際の活用事例までをわかりやすく解説します。
NI分析とは?
「NI分析」とは、Needs(ニーズ)とImportance(重要性)の頭文字をとった分析手法で、
-
顧客や市場のニーズ(Needs)
-
そのニーズの重要度(Importance)
の2軸で評価・整理を行う分析です。
つまり
「お客様は何を求めているのか」
「そのニーズはどれほど重要なのか」
を可視化し、事業戦略やサービス改善に活かすためのフレームワークです。
シンプルですが、顧客志向の強いビジネスにおいて非常に有効な分析方法です。
なぜNI分析が必要なのか?
現代の市場は多様化・成熟化が進んでおり、顧客の要望も複雑化しています。
そのため「なんとなくニーズがありそう」といった感覚的な判断だけでは、事業の成功は難しいのが現状です。
NI分析を活用すれば
✅ ニーズの把握
✅ そのニーズに対する優先順位付け
ができ、より効率的にリソースを集中させる戦略を立てられます。
NI分析の進め方
では、実際にどのようにNI分析を進めるのか、基本的な流れを紹介します。
-
ニーズの洗い出し
アンケート調査やヒアリング、SNS分析などを使い、顧客の声を幅広く集めます。 -
重要度の評価
集めたニーズの中から、どの項目が顧客にとって本当に重要なのかを数値化・ランク付けします。 -
マトリクスで整理
縦軸にニーズの大きさ(需要の強さ)、横軸に重要度をとり、マトリクスに配置します。 -
優先事項の決定
マトリクスの右上(ニーズが大きく、かつ重要度が高い領域)の要素を優先して取り組む施策として決定します。
NI分析を活用した事例
例えば、ある飲食チェーンが
「ファミリー層をもっと取り込みたい」という課題を抱えていたとします。
-
アンケートでニーズを調査したところ
「子連れで入りやすい雰囲気」「お子様メニューの充実」
といった声が多かった。 -
さらに、子育て世代にヒアリングした結果
「お子様メニューの品数が少ないのは致命的」
という強い要望があった。 -
これをNI分析で整理すると
「お子様メニューの充実」がニーズも大きく重要度も高いと特定できたため、
新メニュー開発に集中する施策を打つことができました。
結果として、ファミリー層の利用率が向上したという実例があります。
まとめ
NI分析は
✅ 顧客の「求めていること」
✅ その「優先度」
をしっかり可視化できるシンプルで強力なフレームワークです。
競争が激しい市場環境で勝ち残るためにも、ぜひNI分析を活用してみてください。
NI分析テンプレート(例)
以下のフォーマットで整理すると、誰でも簡単にNI分析を進められます。
エクセルなどに転記してそのまま利用してもOKです。
✅ 1. ニーズ洗い出しシート
| No. | 顧客の声・要望 | ニーズの内容 | 出典・根拠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 例: 小さい子どもと一緒に食事しやすいお店が少ない | ファミリーで入りやすい飲食店 | アンケート(n=100) |
| 2 | 例: お子様メニューがワンパターンすぎる | 子ども向けメニューの多様化 | 店舗スタッフヒアリング |
| 3 |
→ できるだけ多くの「顧客の声」をこの表に集めてください。
✅ 2. ニーズの重要度評価シート
| No. | ニーズの内容 | ニーズの大きさ(需要の強さ) | 重要度(顧客の優先度) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ファミリーで入りやすい飲食店 | 4(5段階) | 5(5段階) | 利用頻度が高い層からの声 |
| 2 | 子ども向けメニューの多様化 | 5(5段階) | 5(5段階) | 競合との差別化要因になる |
| 3 |
→ 5段階評価などを用いて定量的にスコアをつけるのがおすすめです。
✅ 3. NIマトリクス
最後にマトリクスで優先度を視覚化します。
縦軸に「ニーズの大きさ」、横軸に「重要度」を配置します。
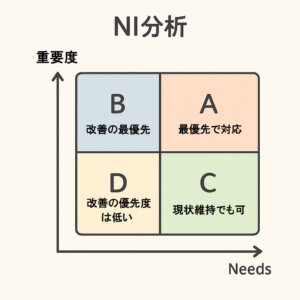
-
右上エリア(重要度大・ニーズ大) → 最優先で取り組む
- 左上エリア(重要度大・ニーズ小) → 潜在市場の掘り起こし
-
右下エリア(重要度小・ニーズ大) → 時期をみて検討、現状維持でも可
-
左下エリア(重要度小・ニーズ小) → 優先度低い
テンプレートの活用ポイント
✅ データは必ず「顧客の声」から集める
→ 感覚や社内視点だけでなく、実際のアンケートやSNSの口コミなどを基にする
✅ 項目はできるだけ定量化(数値化)する
→ 客観的に比較がしやすくなる
✅ メンバー複数で評価する
→ 主観に偏らないように、複数人でスコアを出す
このテンプレートを使えば、初めてNI分析を導入する企業やチームでもスムーズに始められるはずです。
NI分析の導入手順
✅ ステップ 1:目的を明確にする
-
何のためにNI分析を行うのかを決めます。
例:-
新規サービス開発
-
既存サービスの改善
-
顧客満足度向上
-
-
目的が曖昧だと分析の方向性がぶれてしまうため、必ずチームで合意しておきましょう。
✅ ステップ 2:情報を収集する
-
顧客アンケート
-
インタビュー
-
SNSやレビューサイトの口コミ
-
社内の顧客接点担当者(営業・カスタマーサポートなど)からのヒアリング
など、生の顧客の声を幅広く集めます。
ポイントは、
👉 数を多く集める
👉 具体的なエピソードを拾う
ことです。
✅ ステップ 3:ニーズを洗い出す
-
収集した情報を分析し、どんなニーズがあるのかを項目ごとに整理します。
-
重複しているものはまとめて、表にリスト化しましょう。
(テンプレートの「ニーズ洗い出しシート」を活用すると便利です)
✅ ステップ 4:重要度を評価する
-
洗い出したニーズに対して、
-
どれだけ多くの顧客が求めているか(需要の大きさ)
-
そのニーズの優先度はどの程度か
を、5段階などで評価します。
-
-
評価には、社内の複数メンバーの視点を取り入れると偏りを減らせます。
✅ ステップ 5:マトリクスに整理する
-
重要度(横軸)
-
ニーズの大きさ(縦軸)
でマトリクスを作成し、
各ニーズをプロットして可視化します。
→ 右上の領域(重要度・ニーズともに高い) に入ったものを優先的に施策化します。
✅ ステップ 6:アクションプランを決定する
-
マトリクスで抽出した優先度の高い項目に対して
-
どのような施策を行うか
-
いつまでに
-
誰が
を決め、具体的なアクションプランに落とし込みます。
-
✅ ステップ 7:定期的に見直す
-
顧客ニーズは時代や環境で変化します。
-
NI分析も一度きりではなく、半年〜1年に一度は再評価する仕組みにすると、変化に追随しやすくなります。
NI分析導入のポイント
✅ 顧客の声が命
→ 社内の思い込みだけで判断しないこと
✅ 数値化・可視化が重要
→ あいまいな表現ではなく、必ず数値で示す
✅ チームで進める
→ 一人で完結させず、複数の意見を交えてバランスをとる
これらの手順を踏めば、
「ニーズは分かっているつもりだけど、優先順位が決められない」
という状態をしっかり打破できます。





